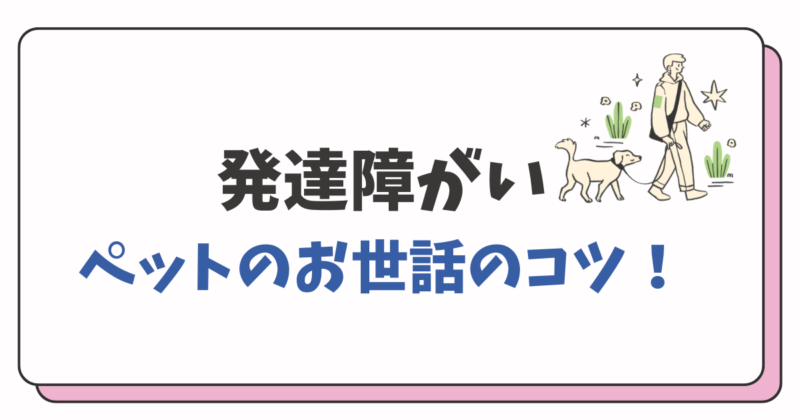
どうしてペットのお世話ができないの?発達障害の子の特性とは
「えさくらいあげてほしいな。」
「散歩をお願いできないかな?」
「トイレ掃除は難しいかな。」
すこしでも手伝ってほしい、そんな気持ちになることはありませんか?

こんにちは!
特別支援学校歴15年の就労支援員のちゃい@chai20100527です。
私もペットを飼っているのでお世話してもらうための方法解説していきますね!
発達障害のある子は、「やりたい」という気持ちがあっても、行動につながらないことがあります。
「昨日はできたのに、今日は全然やらない…」と感じることもあるかもしれません。
でも、それにはいくつかの理由があります。
興味のあることに集中しすぎる
好きなことに集中すると、他のことが見えなくなってしまう子が多いです。
ペットのお世話の時間になっても、頭の中がゲームや本でいっぱいで、気づかないこともあります。
どうしても「今」やりたいことに集中してしまうのが特性でもあります。
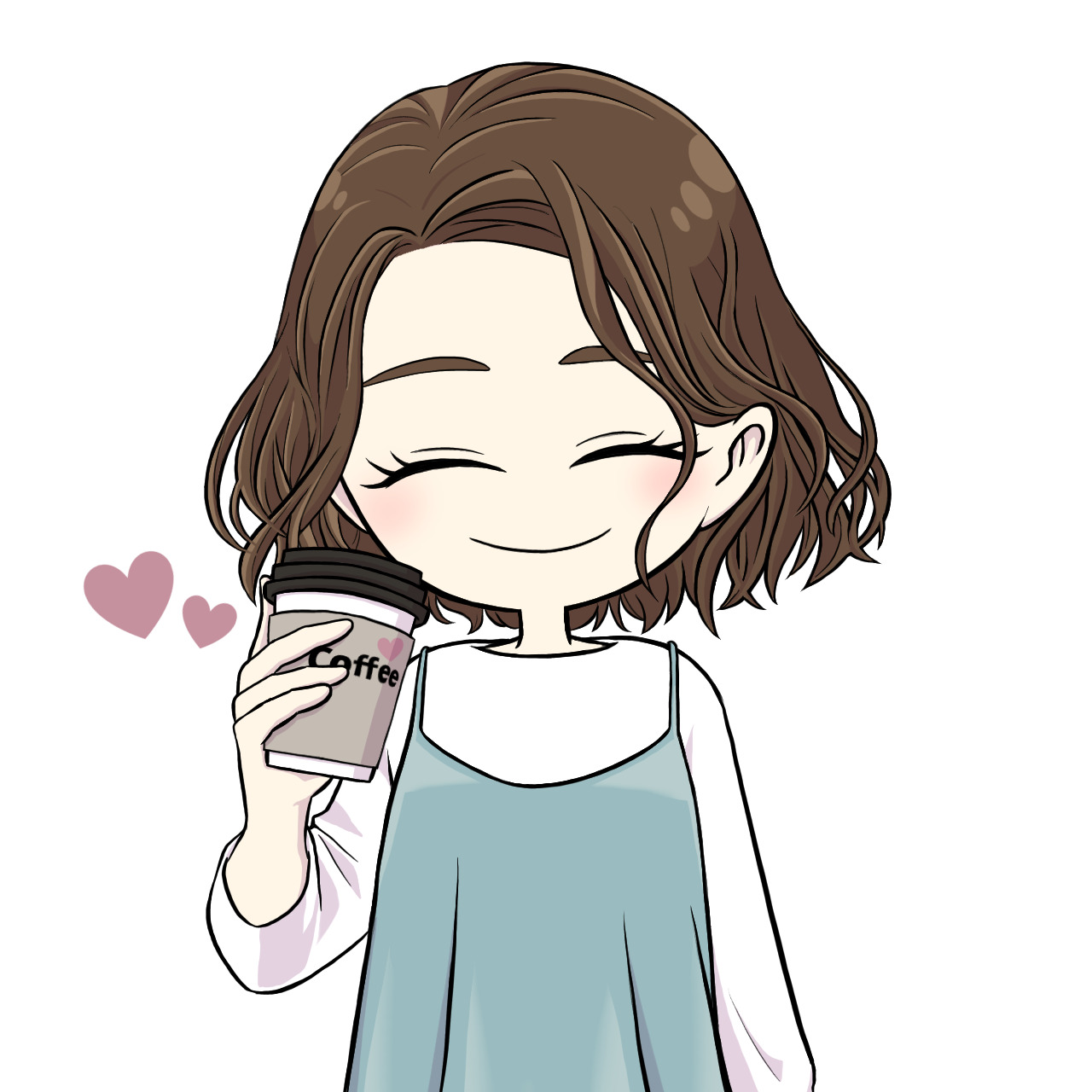
見通しがもてるとまた違ってくるんですけどね。
忘れてしまう・時間の感覚がつかみにくい
「あとでやるね」と言ったまま、すっかり忘れてしまうことがあります。
時計や時間の感覚があいまいで、いつやるかが分かりにくいのです。
「やらなきゃ」と思っても体が動かないことがある
頭では分かっていても、動けないことがあります。
「早くやって!」と何度言っても、かえってプレッシャーになってしまうことも。
本人は、一生懸命切り替えている最中だったりするんですよね。
発達障がいがペットのお世話ができないときの3つの工夫

楽しさを伝える工夫をしてみよう
お世話を「やらなきゃいけないこと」ではなく、「楽しそうなこと」として伝えてみましょう。
例えば、犬のお皿を洗うことも「ピカピカにしてあげよう!」とゲームっぽくしたり、
「お水をあげると喜ぶね!」とペットの気持ちに注目させてみてください。
動物の動画や絵本を一緒に見て、「かわいいね〜」と気持ちを近づけるのもおすすめです。
一緒にやるスタイルで「安心」を増やす
「はい、やって!」と急に1人でやらせるのではなく、「お母さんも一緒にやるよ」と声をかけながら始めてみてください。
最初は見本を見せたり、「お皿を持ってくれるだけでいいよ」と、小さな手伝いから始めるのも◎。
「1人じゃない」という安心感が、やる気につながります。
「今やろうね」の声かけで行動をサポート
「あとでやろうね」は、たいてい忘れてしまいます。
だから、「今やろう!」と短く、はっきり伝えるのがポイント。
「今このタイミングならできそう」というときに、そっと背中を押してあげてください。
タイマーを使って「ピピッとなったら一緒にやろうね」も効果的です。
発達障がいがペットのお世話ができないときは、できたことに目を向けよう
できたタイミングを見逃さずに声をかける
ちょっとでもできたときは、すぐにほめてあげましょう。
「お水、あげられたね!」「見ててくれてありがとう!」
そんな声かけが、次の行動につながります。
お世話が難しければ、他のかかわり方もOK
毎日お世話を続けるのが難しいなら、「なでてあげる」「名前を呼ぶ」など、ペットとの関わり方を変えてみてもいいんです。
役割を家族で分けて、「できること」を増やしていきましょう。
「完璧」より「できた」を積み重ねていこう
最初から全部できなくても大丈夫。
「一つだけでもやれたね」「昨日より一歩進んだね」と、少しずつの成長を一緒に喜んでいきましょう。
まとめ 発達障がいがペットのお世話ができないときは成功体験を積み重ねよう

発達障害がある子にとって、ペットのお世話は「ただやる」だけでも大きな挑戦です。
だからこそ、楽しく・安心して・少しずつ続けることが大切。
今日できなくても、明日できるかもしれません。
お世話を通して「やればできるかも」という気持ちが育つよう、親も一緒に寄りそっていけたら素敵ですね。
ペットを飼うことで、気持ちも癒されて精神的にも落ち着いてくることもあります、みんなで協力しながらお世話できるといいですよね。
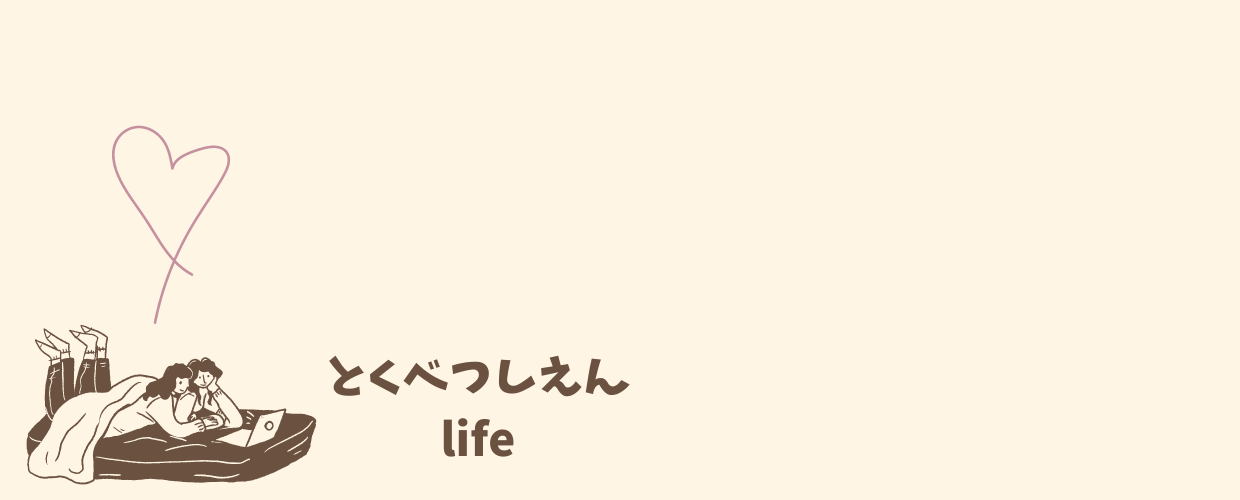
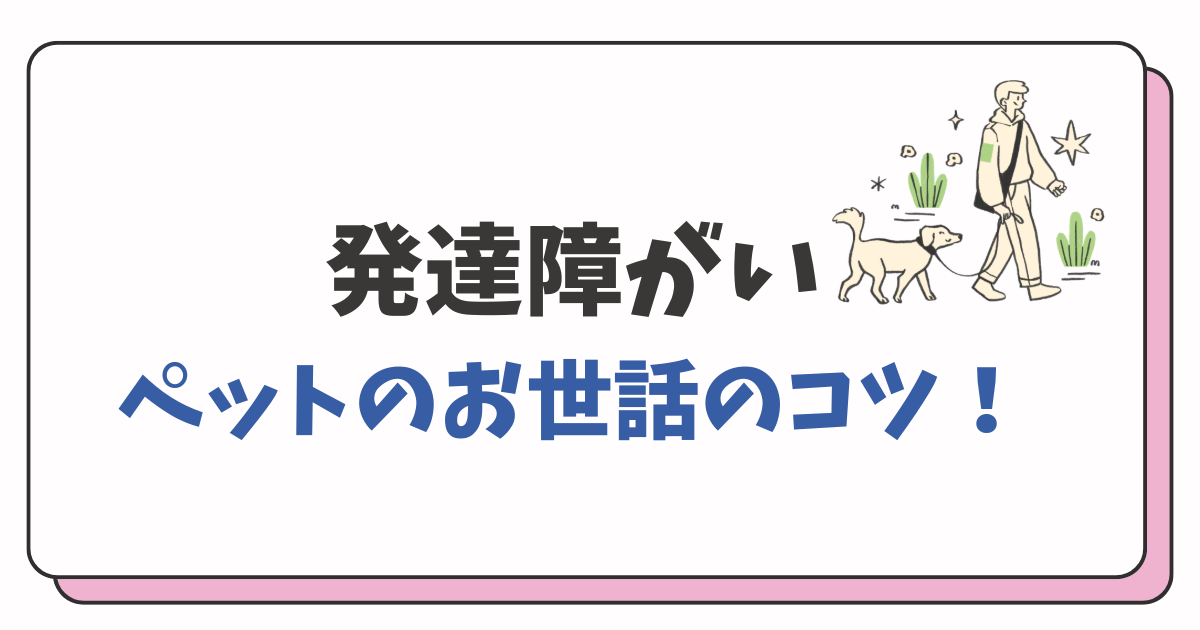
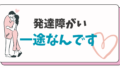
コメント